任期途中の役員を退任させるには
~役員退任のアレコレ 任期が残ってる場合はどうすればよいか~
前回、「役員の任期は何年にすべき?」という所長コラムを投稿しましたが、今回は任期途中の役員を退任させる方法を、司法書士の視点から解説いたします。
■ 会社法が定める「退任」要件
会社法上、株式会社の取締役が退任する主要な事由として、以下のものが定められています。
・辞任(会社法330条、民法651条)
・欠格事由の発生(会社法331条)
・任期満了(会社法332条)
・解任(会社法339条)
今回は、「辞任」「任期満了」「解任」にスポットを当てて、それぞれの手続き解説していきます。
■ 辞任
取締役を退任させる場合、最もオーソドックスな手続きは、当該取締役に辞任届を提出させ、退任してもらう手法です。
注意事項として、辞任により、取締役の員数が会社法又は定款の定める数を下回る場合、辞任した取締役は、欠員状態を解消するまで取締役としての権利義務を逃れることができません(会社法346条1項)。
例えば、取締役会を設置している株式会社の場合、取締役を最低でも3人以上置く必要があります(会社法331条5項)。
取締役がA・B・Cの3人しかいない取締役会設置会社の場合、Aは辞任届を提出しても、
・新たに取締役を選任する
・取締役会を廃止する
までは、取締役の地位に留まることとなります。
また、取締役は「会社に不利な時期」に辞任した場合、やむを得ない事由があったときを除き、会社の損害を賠償しなければなりません(会社法330条、民法651条1項)。
辞任に関して、会社と取締役で合意があったことを明確にするため、取締役が署名・押印した辞任届を作成することを強く推奨します。
■ 任期満了
取締役が任期満了するタイミングの定時株主総会で、当該取締役を再選しなかった場合、その取締役は自動的に退任となります。
ただし、上記「辞任」と同様、退任により取締役の員数を欠く場合は、欠員状態を解消するまでは取締役としての権利義務が残ります。
この場合、辞任届の作成等の特別な手続きはありませんので、一番事務処理・係争の少ない手法と言えるでしょう。
また、取締役改選期の定時株主総会以外のタイミングでも、株主総会の特別決議により定款を変更し、取締役の任期を短縮することで、同様に取締役を退任させることができます。
例えば、取締役の任期を「10年」に設定している株式会社が、取締役Aが選任から5年を経過している状態で、任期を「2年」に変更する定款変更を行った場合、定款の効力発生と同時にAは自動的に退任します。
ただし、上記定款変更により、強制的に退任をさせたケースでは、会社に当該取締役への損害賠償を命じた判例が存在するため、注意が必要です(東京地裁平成27年6月29日判決、他)。
■ 解任
退任させたい取締役が辞任に応じない場合は、株主総会による解任の手続きによることも可能です。
株式会社は、株主総会の普通決議により、いつでも取締役を解任することができます。
解任の場合は、「辞任」や「任期満了」と異なり、取締役の員数を欠くこととなっても、当該取締役は権利義務を有しません。株主から解任されるような役員を法令により残留させることは好ましくないためです。
なお、解任について正当な理由がある場合を除き、当該取締役は株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。
取締役はもともと、定款で定められた任期を見込んで会社と委任契約を結んでいるので、任期途中で正当な理由なく解任された場合、残存任期期間中の役員報酬などが損害に含まれる形となります。
■ 司法書士のアドバイス
役員をその意に反して退任させる場合、会社の株主構成や定款の規定など、様々な要素を総合的に考慮して慎重に手続きを進める必要があります。
最も重要なのは、会社と役員の間で紛争が生じないよう、あらかじめ適切な任期の設定や、報酬体系の確立など、事前にガバナンス体制を整えておくことです。
当事務所では、登記にとどまらず、会社様の個性に応じたガバナンス設計のアドバイスが可能ですので、会社設立時の段階であっても、お気軽にご相談ください。

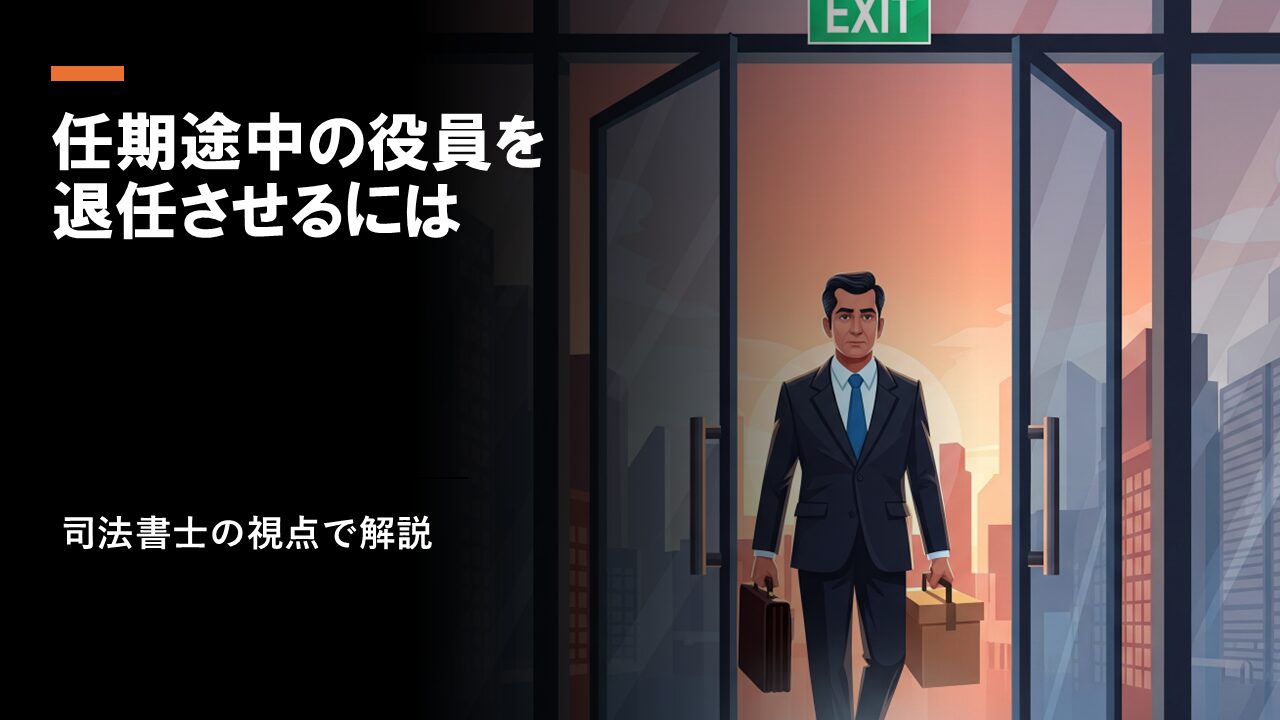


コメント