2025年の夏は、日本の戦後80年の節目の夏でもあります。
戦後の高度経済成長期は目覚ましいものでしたが、適切な法的手続きを経ずに開発が進められたことによる、市民と行政との間の法的トラブルが、昨今になって表面化するケースを良くお見かけします。
例えば、私有地である土地が公道として長らく使用されていたり、はたまた逆のケースも然り、といった場合です。
今回はその中でも特に専門的なケースではございますが、海を埋め立てた土地の時効取得の可否について、最高裁の判決を参照しながら、司法書士の視点から解説していきます。
法律上の「不動産」の定義
まず、日本法における「不動産」とは、土地およびその定着物を指します(民法86Ⅰ)。
この点、一般に海や河川の水面は、「特定の者が排他的に支配するもの」ではないため、所有権の客体とならず、水に覆われたままの状態で個人が所有することはできない、と最高裁で判示されています(最判昭61年12月16日)。
一方、海や河川に関しても、これを埋め立てて土地が形成され、公有水面埋立法に基づく竣功認可がされることにより、個人の所有権の客体となる「土地」になります。
そのため、例えば家の近くの河や海辺を勝手に埋め立てて長期間占有したとしても、上記竣功認可を取得しない限り、その区画の所有権を時効取得することはできません。
しかし、例外的に竣功認可を経ていない場合であっても、埋立地の時効取得を認めた判例があります。実際の裁判の事例を交えながら、「埋立地」の時効取得の可否について解説していきます。
最判平17年12月16日
竣工認可が完了しないまま放置された埋立地について、黙示的な公用廃止とみなし、個人による時効取得を認めた判例が、平成17年12月16日の最高裁判決です。
事例の概要は以下のとおりです。
- 戦後間もなく、Dが大分県の海面を埋め立てるも、竣功認可を取得せずにEに売り渡す
- Eは販売用の松を植樹するなどして本件各埋立地の占有を開始
- Fが相続により本件各埋立地の占有を承継し、20年の期間を経過
- Fの相続人が、取得時効の完成による所有権確認訴訟を提起
上告審である最高裁では、「竣功認可を受けていない埋立地が所有権の対象になるか」が争点となりましたが、最高裁判所第二小法廷では、以下の条件すべてを満たす場合、例外的に竣功認可を受けていない埋立地であっても、黙示的な公用廃止により私法上所有権の客体となる「土地」として認められ、取得時効の対象となる、と判示しました。
黙示的な公用廃止の要件
公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地であっても,
- 長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され,
- 公共用財産としての形態,機能を完全に喪失し,
- その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが,
- そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく,
- これを公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合
土地として私法上所有権の客体になる。
以上は埋立地に関する判例ですが、この「黙示的な公用廃止」という概念は、河川や道路など、公共用物全般に適応可能です。
司法書士からのアドバイス
相続によって取得した土地を精査したところ、実は家屋の一部が公道上にあった、というような例も少なくありません。
時効取得に関する交渉は、法律に則って適切な手順を踏む必要があり、少しのミスが重大な不利益へと繋がりかねません。
時効取得や、行政との境界にお悩みの方は、ぜひ一度弊所までお気軽にご相談ください。
問題を多角的に分析し、最適な解決策をご提示させていただきます。


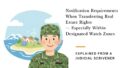

コメント