ご依頼いただいた業務の完了後、報酬をお受け取りする際には、司法書士として領収証を発行しております。
経理にお詳しい方の中には、「あれ?印紙が貼っていない?」と、司法書士が発行する領収証の様式に違和感を持たれることもあるかもしれません。
実は、司法書士などの「士業」が発行する領収証には、一般的な事業者とは異なる独自のルールが存在します。
今回は、司法書士作成の領収証の特徴について、司法書士の視点から解説していきます。
司法書士の領収証は作成・保管が義務
一般の事業者の場合、領収書の発行義務は依頼者から請求があって初めて生じます(民法486条)。
領収書の発行を特段求められなかった場合は、発行しなくても構いません。
(民法)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
一方、司法書士については独自の規定により、依頼者から報酬を受けた際には、請求の有無に関わらず、領収証を作成し、3年間保存する義務があります(司法書士法施行規則29条)。
(司法書士法施行規則)
第二十九条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
司法書士の領収証には職印の押印が必須
司法書士が作成する領収証のうち、依頼人に交付する正本に関しては、司法書士の職印を押印しなければなりません。
司法書士会に登録している司法書士は、必ずその職務上の印鑑、「職印」を登録し厳重に保管しておりますので、領収証に職印を押印することにより、受任した司法書士本人が領収証を発行した事実を担保しています。
司法書士作成の領収証には印紙が不要
売上金額が5万円以上の、営業に関する書面の領収書については、売上金額に応じた収入印紙を添付しなければなりません。
バーベキューの買い出しなど、一度に大口の買い物をした際、レシートの右上に200円の印紙が貼られているのを見たことがある方もいらっしゃると思います。
しかし、司法書士などの士業の行う行為については商行為に該当しないとされているため、基本的に5万円以上の領収証を発行する場合であっても、収入印紙の添付が必要ありません。
(印紙税法基本通達別表第1第17号文章の26)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
ただし、例外として、司法書士法人が発行する領収証については、通常の領収書と同様に、印紙を添付しなくてはなりません。
(印紙税法別表第一(課税物件表)第十七号の非課税物件欄2に規定する営業)
会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの
なお余談ではありますが、上記の通り、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができる法人が発行した領収証については営業に関するものとして扱われ、収入印紙を貼付しなければなりません。
一方、利益金又は剰余金の配当又は分配が法令で禁止されている医療法人などは、法人化していても領収証への印紙の貼付は必要ないのです。
司法書士からのアドバイス
日常業務の中で何気なくやり取りしている領収証にも、実は様々な法的ルールが存在しています。
特に士業との取引においては、印紙税の有無など、通常の事業者とは異なる点があるため、会計処理の際には一度ご確認いただくと安心です。
弊所発行の領収証についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談くださいますと幸いです。

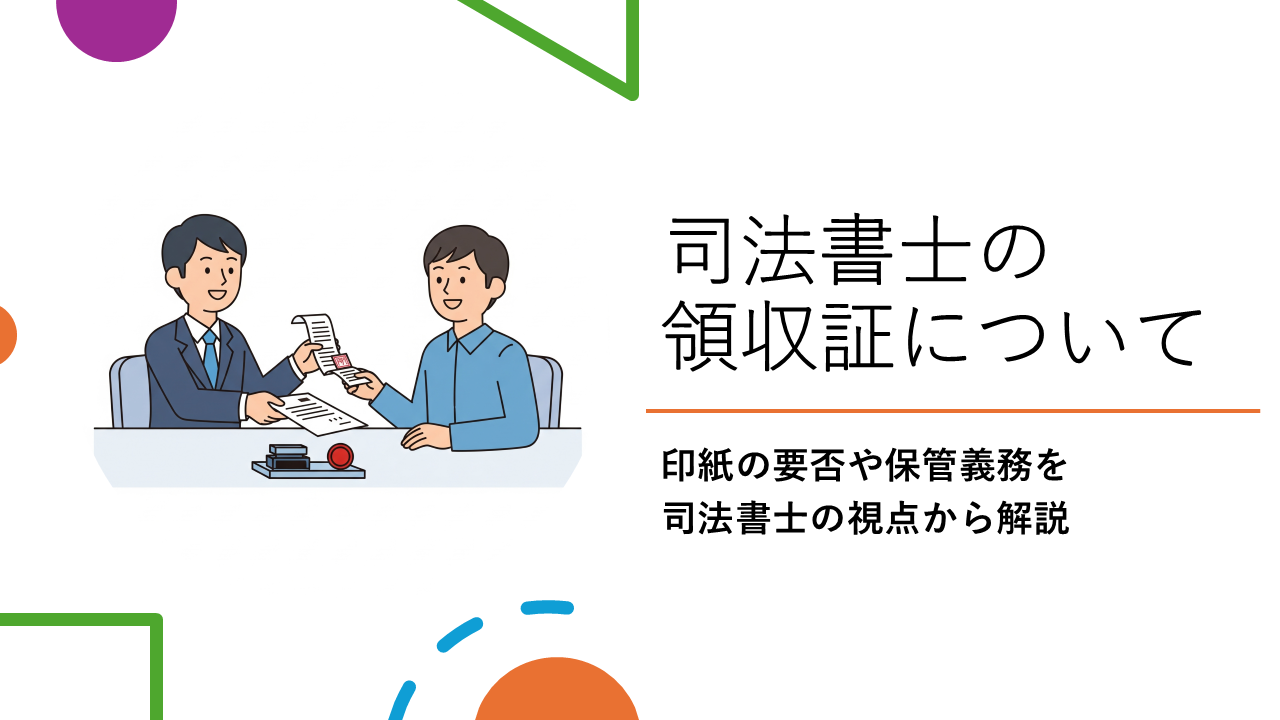


コメント